とりあえずマイボトルを買おう!
初期費用はかかりますが、マイボトルを買えば1、2ヶ月で元が取れます。
安いものでは1,000円台からあり、3,000円台であれば結構立派なものが買えます。
節約を始めるには、とってもハードルは低めです。
何年も使うことを考えれば、少し高めの方を選んだ方が良いと思います。
1ヶ月の節約金額
150円のペットボトルを1日1本買うと想定して、1ヶ月22日出勤または登校で計算すると・・・
150円 X 22日 = 3,300円
1日2本買う人は・・・
3,300円 X 2 = 6,600円
結構バカに出来ない金額ですよね。
1年で計算すると1本買う人で39,600円、2本買う人で79,200円の節約になります。
近場なら旅行に行けそうですね。
中に入れる麦茶やコーヒー代は別にかかりますが、激安なものは探せばいくらでもあります。
マイボトルを持つことは恥ずかしくない!

女性がマイボトルを持つことは、今じゃ結構当たり前という感じですが、男性はなんか恥ずかしい、男らしくないと思っている人多いんじゃないですか?
そう思っていることが男らしくないです。😁
無計画が男らしいなんてことはありません。
むしろ計画的で将来のことを考えている人の方が立派じゃないですかね。
無理しないのが継続出来るコツ!
マイボトルを持っているから、ペットボトルを買ってはいけないというルールを決めると苦しくなってしまいます。
夏は喉が渇きますし、冬はあったかいコーヒーや紅茶が飲みたくなることもあります。
新作のジュースが気になることも当たり前です。
ペットボトルを買いたい時は、買ってもいいんです。
マイボトルを飲み干してしまう場合もありますから・・・
そういう時は、無理せずぺットボトル買って飲みましょう。
無理しないのが継続の秘訣です。
私もたまに買ってます。😊
マイボトル選びを失敗しないポイント

自分に合ったサイズを選ぼう
マイボトルを買う時は、自分が1日どのくらい飲み物を飲むのかを考えて、サイズを選びましょう。
たくさん飲む人が小型のマイボトルを選ぶと量が足りなくて、結局ペットボトルを追加して買うことになり節約の目的が達成出来ません。
またあまり量を飲まない人が大きいマイボトルを買うと、ただ重いだけになります。
サイズ選びは、とっても重要なポイントです。
飲みやすさを重視して選ぼう
毎日持ち歩くものです。
人それぞれ飲みやすさ、飲みにくさは違います。
こぼしやすいと感じて毎日飲み続けるのは、ただただストレスです。
蓋を開けた形状も良くチェックしてから買うことがポイントです。
ネットで購入する時は、飲み口の写真や口コミをチェックしましょう。
カバンとの相性をチェックして選ぼう

これは結構重要で、太いマイボトルを買ったけどカバンに入れたらパンパンになってしまうなんて最悪ですよね。
自分のカバンに合う長さ、太さのマイボトルを選びましょう。
だからといってカバンに入れてしまうと、万引きと間違えられてしまうので注意が必要です。
あくまでイメージで留めておきましょう。
デザインで選ぼう
毎日持ち歩くものです。
好みの色、形を探し、飽きが来ないように
テンションが上がるおしゃれなデザインを選びましょう。
洗いやすいものを選ぼう
毎日洗うものなので、出来るだけ洗いやすく、時間短縮できる形状を選びましょう。
節約以外のメリット
ペットボトルをカバンに入れて持ち歩くと夏はすぐにぬるくなり、冬は冬でホットがすぐにぬるくなります。
その点マイボトルの場合、氷を入れておけば長い時間冷たさをキープ出来ますし、冬でもホットがまあまあキープ出来ます。
飲みたい時に適温で飲めるのは、マイボトルのメリットです。
マイボトルの中身で楽しもう
間違ってもペットボトルを買ってきて、マイボトルに入れるのはやめましょう。
それでは節約になりませんので、本末転倒です。
麦茶やお茶のティーバックや粉コーヒーなどなるべく安くて、おいしい種類のものを探すのも楽しみの一つになりますね。
日によって中身を変えるのも飽きないポイントですね。
まとめ

このページを見てくれた方は、節約に興味のある方だと思います。
ただ節約といっても具体的に何から始めたらいいのか分からない。
大きなことから始めるのは面倒だという方は節約の練習としてマイボトルから始めてみませんか。
きっと節約意識が芽生えるはずです。
まずはそれでいいんです。
初めてみるとマイボトルを持つことがすぐに当たり前になり、苦労なく日々節約が出来るようになっていきます。
節約の大切さを知る第一歩としてスタートすると、他の節約にも興味を持つきっかけになります。
そうなればもっと節約効果の出る固定費の削減にも積極的に取り組むことが出来るようになります。
節約することがどんどん楽しくなってきますよ。
たかがマイボトル。
されどマイボトル。
試しに始めてみてはいかがでしょうか。
固定費の節約についても記事を書いています。
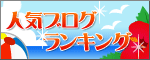
人気ブログランキング



